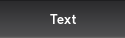存在の耐えやすい軽さ(3×3=9)
森繁映画を観ていると山茶花究(さざんかきゅう)という俳優が気になってくる。こんなときはウィキペディアに解説してもらおう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E8%8C%B6%E8%8A%B1%E7%A9%B6
左翼思想に傾倒し、特高にも目をつけられ、尾行を巻いているうちに浅草のレビュー小屋に潜り込んで、そのまま文芸部員としてレビューの台本を書いたり、また歌手として舞台で歌ったりして生計を立てるようになる。
1932年11月にカジノ・フォーリーで歌手としてデビュー。1933年1月に浅草オペラ館の俳優となる。エノケン劇団、万盛座のグラン・テッカールと転々としたのち大阪に戻り、いくつかの舞台に立つが、芽が出ずに俳優を辞めて朝鮮に行き、実業につく。1937年8月、東宝のロッパ一座に入り役者に復帰。このとき一緒に入ってきた森繁久彌と出会う。ここで芸名を加川久と名乗る。
1939年3月、当時絶大な人気を得ていた「あきれたぼういず」がリーダーの川田義雄を残して、坊屋三郎、益田喜頓、芝利英が吉本興業から松竹系の新興キネマ演芸部に引き抜かれ、その川田の代役として選ばれ、山茶花究の名で第2次あきれたぼういずを結成する。1943年に解散、森川信の新青年座に副座長で入り、1944年に山茶花究劇団を組織して巡業するが、戦況の悪化により解散する。その後、水の江滝子主催の劇団たんぽぽに加わり、終戦を迎える。
敗戦直後の1945年10月に再び劇団を立ち上げるが、すぐに解散。1946年に坊屋三郎、益田喜頓と「あきれたぼういず」を再結成。1952年に解散後は、喜劇役者として舞台や映画で活躍。ラジオのジャズ番組の司会などをしていたところ、森繁久彌から誘われて映画『夫婦善哉』にふちなし眼鏡をかけたインテリの番頭役で出演、冷酷で神経質なキャラクターを嫌味たっぷりに演じ、性格俳優として飛躍。
やはり一番印象に残っているのは『喜劇 とんかつ一代』のキャラクターだ。アムステルダムの世界大会で優勝したという職人らしいが、何の職人かは中盤まで明かされない。只者じゃない雰囲気から、カンナビスカップの優勝者?なんて邪推してしまうのだが、実は普段は冷静、だが怒ると豚と人間の区別が付かなくなるというおそろしい屠殺職人という設定。しかも病的な清潔マニアという今じゃ絶対に映画に出てこれない最高のキャラを演じているのだ。
前回のブログで扱った『森繁自伝』に山茶花究のことが書かれていたので引用しておこう。古川緑波親父の大ボンが森繁、中ボンが山茶花、小ボンが三木のり平という腐れ縁のアフェニティーグループを形成していたようだ。
ここで親しき悪友山茶花究のことについて少し触れておきたい。すでに脇役として押しも押されもせぬ手がたい役者として映画に活躍し、また私の芝居には欠かせぬ女房役をつとめてくれる彼は、私の友達のなかでも風変わりに属する最たる奴で、友達づき合いは悪くないが、限界以上に親しくなろうとせぬ男である。わずかに私と三木のり平くらいが一番親しくしているぐらい。彼は友達ほど<面倒くさい>ものはないという。そんな孤独のせいか、熱帯魚にこったり、模型飛行機にこったり、一人で楽しむことに妙にこる男で、それも自分のピークまでくると、さッと全部人にくれてやって、また新しい道楽をさがすのである。ただ驚くのは、むさぼるように本を読むことである。
飽くなき探究心とピークに達した後の執着のなさ、つまりはその「軽さ」に憧れるわけだが、なかなかこれは真似をすることができない。ボクは、欲張りな性質なのでいろいろなものに興味を持つのだが、どれもピークに達する気配がなく、いや、ボクの場合は高みに昇るというよりは、地下深く掘っていく方向に進むのだが、どの分野においても底が見える気配がしないのだ。同時進行に興味の趣くまま掘っていくと、深い処で異質だと思っていたものが繋がってしまったりして、どんどん欲望は増幅されるばかり。捨聖、一遍上人のようには生きられないにしても、なるべく身軽に生きたいもんである。
「軽さ」への憧れによる物事に執着したくない、というボクの執着心の重さはいかほどか。

駄々っ子森繁の重力に抗する山茶花究(左)と淡島千景(右)
- HarpoBucho
- By harpobucho / Jan 17, 2010 11:16 am