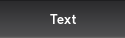マーク・デリー
Culture Jamming
「どうやって幻影と戦うべきなのか?」
いいかえるなら、表徴の帝国でメディアと戦うにはどのような政治手段が考えられるだろうか、という問題。
その答えは、ウンベルト・エーコのいう「記号的ゲリラ戦争」の中に見つかるかもしれない。エーコは書いている。
「メディアのメッセージを受け取る人々には、まだ自由が残されているように思われる。それは、別の方法でメッセージを読みとっていくという自由だ———視聴者がメッセージと多様な解釈の可能性をコントロールするように説く行動を私は提唱したい」
「メディアを利用して、他のメディアにおける選択肢を伝えることは可能である———コミュニケーション・ゲリラの集団は、テクノロジカル・コミュニケーションの世界の番人である。彼らはメッセージが盲目的に受容される状況に対し、批評の次元をとりもどすだろう」
エーコは演繹的に、ビジュアル・リテラシーというラディカルな政治手段を想定している。ビジュアル・リテラシーとは、消費者文化評論家のスチュワート・ユーウェンによって強く主張されている概念だ。ユーウェンはいう。
「われわれは、イメージが伝達の形式を支配している時代を生きている。それは、意味の構造化において他の形式をしのいでいるのだ」
熱と光と、電子のポルターガイストの社会———無限の広さを持ち、光がきらめき、滑らかでつやのある製品があふれるような不気味な別世界———においては、意味を再構築しようという試みは、およそ無謀なものである。企業のマーケティング部やPR会社の考え方を正そうとすることさえ同様だ。だからビジュアル・リテラシーというゴーストバスターズが必要なのだ。
このコミュニティ「カルチャー・ジャミング」について説明しよう。「ジャミング」とは、CB無線で使われるスラングで、おならの口まねや、卑わいな言葉、そのほか同じような子供じみたやり方で、ラジオや仲間同士の無線の会話を妨害することである。これに対してカルチャー・ジャミングは、かつてないほど便利になった一方、押しつけがましくもなったテクノ・カルチャー———記号を操作して、社会的合意をでっち上げている———をその標的とする。
「カルチャー・ジャミング」という言葉は、コラージュバンドのネガティヴランドによって初めて使われた。彼らは、屋外広告の改竄などメディアを妨害するさまざまな行為に対してこの言葉を使ったのだ。アルバム『JAMCON `84』で、メンバーの一人がシリアスめいて述べている。
「われわれの生活が、いかにメディア環境に影響を受け、支配されているかということについて、皆気づきはじめた。そしてそれに抵抗する者も出てきた—屋外広告をみごとに改竄すること—それは、見る者に、広告を製作する企業の戦略について考えさせることになる。カルチャー・ジャマーにとって、スタジオは世界全体なのだ」
カルチャー・ジャマーは芸術的なテロリストであり、生まれつきの批評家でもある。彼らはエーコのいうコミュニケーション・ゲリラのように、送信機から受信機へ至る途中の信号にノイズを挿入し、受け手に予期しない解釈を促すのだ。彼らは侵入物に侵入し、広告やニュース番組、その他のメディアに破壊的な意味を付与する。同時にメディアを解読し、そのうわっつらの魅力をはぎ取ってしまう。ジャマーは、決まり文句と偽りに満ちたメディアとの戦争では著作権など存在しないということについて、反論できない証拠を提示する。ユーウェンのいう文化的暗号使用者のように、彼らは受け身の買い物客であることを拒否し、社会的なディスクールの認識を塗り替えていくのだ。
最後に、重要なことだが、カルチャー・ジャマーはグーチョ・マルキストである。彼らは“fun”の感覚を忘れずに、楽しみながら暴力的なイデオロギーを破壊していくのだ。生粋のイタズラ者である元デッド・ケネディーズのボーカリスト、ジェロ・ビアフラはかつてこのように述べている。
「単なる犯罪とクリエイティヴな犯罪とは全く異なるものだ。単なる犯罪というのはセブンイレブンで強盗するようなこと。クリエイティヴな犯罪というのは一つの表現形式だ。それは———魂を高揚させる。この蟻塚のような社会で生き残るにはどうしたらいいだろう? 社会を誘惑するマスメディアを罵ることよりももっといい方法とはなんだろうか? 一日一回悪戯をしかけて、犬を首輪から解き放とう!」
ジャミングは歴史的に連綿と続いてきた行動の一部だ。ロシアのサミズダート(政府の検閲に抵抗した地下出版)、ジョン・ハートフィールドの反ファシズムのフォトモンタージュ、シチュアシオニストのデトーナメント(グリ-ル・マーカスが著書『Lipstick Traces』で定義したもので、芸術品をそれ自身のコンテクストから盗みとり、自分の考えたコンテクストの中に流用してしまう)、ポール・クラスナーやジェリー・ルービン、アビー・ホフマンといった60年代の運動家たちのアンダーグラウンド・ジャーナリズム、ペンタゴンを空中浮遊させようというイッピーたちの街頭演劇、ダラスのサブジニアス教会のようなパロディ宗教、「意味のない情報を必要とする変人のための雑誌」と銘打たれたプロセスド・ワールド誌が報告する種のサボタージュ、アース・ファースト!がおこなう環境破壊に対する妨害行為、ラジカルな理論家、ハキム・ベイが「詩的テロリズム」(コンピューターが業務を進める銀行のロビーで一晩中奇怪な身ぶりで踊ること、国立公園の中に奇妙なエイリアンの遺物のようなアートをまき散らすこと)と呼ぶような、(アントナン)アルトー主義者たちの無意味な行為の数々、ウイリアム・バロウズが『Electronic Revolution』(「連想の道筋を放棄することでマスメディアのコントロールから脱することができる。カット・アップ・テクニックは、幻想によってマスメディアを無力にしてしまうだろう」)のなかで提示している「カット・アップ・コラージュ」の反逆的な使用、サブカルチャーのプリコラージュ(社会的アウトサイダーたちによる、優位文化と結びついた記号の組み替え。浮浪者、ゲイ、ほとんどが非白人のドラァグ・クイーンたちによる、きらびやかな衣装とヴォーグのモデルのポーズの盗用)。
柔軟なカテゴリーであるカルチャージャミングは、多くのサブカルチャー的行動を受け入れる。組織や企業の悪行を暴露する目的でおこなわれる違法なハッキングはその一例だ。また「スラッシング(slashing)」あるいはテキストの改竄行為も含まれる。(「スラッシング」という言葉は「K/S」というポルノ小説に由来している。KIRK/SPOCKの略であるK/Sは、女性のスタートレックファンによって書かれ、アンダーグラウンドのファンジンとして発行されている。スタートレックのストーリーのなかに同性愛的な意味を発見したことから始まったもので、フェミニストたちにも人気がある。私は大衆向けの物語をつくりかえてしまうジャミングの全ての形式に、この「スラッシング」という用語を活用しているので、一般的な言葉として使っている)。
海賊テレビやラジオといったトランスミッション・ジャミング、あるいはビデオカメラによる反=監視行為(DIY精神あふれる暴露屋たちは、警官の蛮行や政府の腐敗を記録するために、コストのかからない技術を利用する)などは、カルチャー・ジャマーにとって可能性に満ちた方法といえる。さらに、まるでいけにえを捧げる儀式のように、マンハッタンのCBSのオフィスの前にテレビを山積みにするといったメディア・アクティヴィズム———湾岸戦争時に FAIR(Fairness and Accurancy In Reporting)によって行われたメディアの偏向に対する抗議行動の一部—や、エイズ報道が少ないことに抗議しておこなった『マクニール/レイラー・ニュースアワー』へのアクト・アップの破壊行動のようなメディア・レンチングなども同様だ。いくぶん伝統的な種のカルチャージャミングは、ペイパータイガーTVのようなメディア監視プロジェクトだ。ペイパータイガーTVは、インディペンデントなプロデュース集団で、情報産業を批評するテレビ番組を製作している。ディープディッシュTVは、草の根の衛星放送ネットワークで、全米のケーブルテレビのパブリックアクセスに自由思想的な番組を供給している。若いアフリカ系アメリカ人のビデオアクティヴィスト集団であるノット・チャンネル・ゼロは「革命—放映中」というモットーを掲げている。そしてアカデミズムへのハッキングが、カルチュラル・スタディーズだ。これは反乱する知識人たちによって、大学の塀の外側から持ち込まれたものだ。
Culture Jamming: Hacking, Slashing and Sniping in the Empire of Signs
Mark Dery
InterCommunication NO.19
進歩的で実践的な未来主義を構築すること
マーク・デリー 電子メール・インタヴュー
毛利嘉孝 訳
http://www.ntticc.or.jp/pub/ic_mag/ic019/059/IC19-059-J.html

Photo=Leah SINGER
Courtesy Grove Press
マーク・デリーは、ニューヨークに脱出したカリフォルニア人だが、いまではアメリカで最も人気のあるサイバー批評家である。『カルチャー・ジャミング』[★1]というパンフレットと彼の編集による論集『フレーム・ウォーズ』[★2]の後で発表された彼の最初の主著『エスケープ・ヴェロシティ(重力脱出速度)』[★3]では、90年代のアメリカのサイバーカルチャーの「ビリビリするようなツアー」を体験できる。この「インフォメーション・エイジの最暗黒部への旅」は、とても簡潔でジャーナリスティックな筆運びで、サイバーデリアのレトリック、サイバーパンクのミュージシャンやポスト = インダストリアルの思想家、「ヴァーチュアル・セックス」の起源、ステラークやオルランといった「儀式の機械工」、そしてハンス・モラヴェックやエクストロピー主義者[☆1]の「廃墟の身体」を正確に描き出している。デリーは、芸術作品、パフォーマンス、インスタレーション、SF文学、映画の分析にあたって、カルチュラル・スタディーズという道具を利用し、サイバー主義者たちのほとんどに深い思考が欠落していることを批判している。
サイバーカルチャーは、そのサブカルチャー的な境界から抜け出すと、新しモノ好きのメディアから突然大きな注目を浴びたのだが、自らのポジションと戦略について明確なパースペクティヴをもつことがなかった(要は未来のことだけ話していたのだった)。イデオロギー的な意味で解放運動に関わっている左翼や文化エリートの視点からも問われることなく、古い(今日では「新しい」)アンダーグラウンドのヒッピー = パンクは、今日でも漠然とした信仰体系を維持しているようにみえる。こういうものを退けて、デリーは、『ワイアード』系デジタル・エリート階級[☆2]のアジェンダである、精神と身体を支配している二分法や、ウィリアム・ギブスンとその追従者にとって当然のように受け取られている「21世紀の分裂病者とザイバツの権力者の麻薬としてのサイバースペース」といったものを、さまざまな角度から疑問に付している。デリーが批判するのは、ニュー・エイジ・イデオロギーの無批判な引用(たとえば、最近のデイヴィスの「オズモース」、マイケル・ハイムの文章、マーク・ペセスのVRML説教)であり、SFの病理学的なファンタジーであり、テクノ = リテラシーの自由の力を強調する一方で、サンフランシスコの現実のストリートの貧困や悲惨さに背を向ける、彼らの「ありえない未来デザイン」やシニカルなネオ・リベラルのグローバリズムなのである。
ヘアート・ロフィンク(以下GL) ——あなたの本『エスケープ・ヴェロシティ』は、文字どおりに身体が重力を克服する速度を扱っているわけではありません。それと対照的に、ポール・ヴィリリオの最近作(皮肉なことに同じタイトルですが)は、そうした問題を扱っています。あなたにとって、サイバーカルチャーとは、何よりもまず、われわれがお互いに話している未来的な物語——神話でありレトリックであり現実逃避の運動でさえあるのです。同時に、あなたの本では、この10年間「デジタル・アンダーグラウンド」が何によって変化してきたのかということがとても面白く描かれています。どのように、この強迫観念的な実践は、社会の辺境で現実の国家と企業の権力と関係しているのでしょうか? 結局は、こういった機械やプログラムやネットワークを作ろうという不気味な欲望は、資本主義のひとつの大きな物語のなかに回収されて終わってしまうだけなのでしょうか?
あなたのオープン・マガジン・パンフレット、『カルチャー・ジャミング——表徴の帝国でのハッキング、スラッシング、スナイピング』の中で、あなたは「カルチャー・ジャミング」という用語を、「情報戦争、テロ芸術、ゲリラ記号学の組み合わせで、われわれが住んでいる情報社会に対抗して導かれているものであり、記号操作を通じた合意の産物によって様式が作動させられる、より一層侵攻的で道具的なテクノカルチャー」とあなたがいろいろなところで定義したものを評価するために使っています。「サイバー・ジャミング」は、たくさんあるわけではありません。破壊/転覆(サブヴァージョン)の神話というものさえ見あたらないようです。90年代は政治ということに関しては本当にそれほど「暗黒時代」なのでしょうか? そして、このナイーヴなテクノトピアの嵐が終わるまでただ待つべきなのでしょうか?
マーク・デリー(以下MD) ——破壊/転覆の神話に死ぬ前の最後の祈りを捧げるのはまだ少し早いように思えます。というのも、それは、一時的自律的領域(Temporary Autonomous Zones)[☆3]というネットの群島や、オンラインや現実の世界におけるその他のアナルコトピア(anarchotopia)といった先端をいくサブカルチャー的な夢の中に生きているからです。たとえば、『ワイアード』は、「制御不能(アウト・オヴ・コントロール)な」[☆4]サイバー資本主義という乱暴で狂ったヴィジョンを魔法のように呼び出し、その典型的な読者である三十過ぎで年収八万一千ドルくらいの知的労働に携わる男性 ——別の言い方をすると、ロバート・ライシュの言う記号の分析者——に、自分たちが一皮むけば自分たちがいまだに十代のミュータント・ニンジャ・ハッカーであると再確認させているのです。『ワイアード』は、活気のある「大したことはない長によって指揮されるサブユニット」からなる「原子化企業」というゴスペルを唄うトム・ピーターズのような経営の導師(グル)の言葉を話しています。『ワイアード』のデザインはまさに、ベビーブーマーたちのファンタジーである「混乱(メッス)のない革命」といったMTVの印象深いスローガンに働きかけ、企業の年次報告書とサイバーデリア的な「スピン・アート」[☆5]の両方に同じように使われているデイ = グロのグラフィックス[☆6]とマイティ・モーフィンのタイポグラフィ[☆7]によって、21世紀のサイバー資本主義とカウンターカルチャーの反乱とを和解させようとしています。キース・ホワイトが、彼の『バッフラー』の中の「キラー・アプリ」というエッセイで書いているように、「企業であるということはいまや退屈なことでも順応主義でもない——それはロックすることなのだ!」という考えは、「新しい存在であることと、社会的に不安定なエリートの一員であることを熱望している」デジタル・エリート階級の気持ちを和らげる音楽なのです。このように、皮肉にも『ワイアード』によって経営者に点火され、蹴込まれ、ジャックインされた擬似的革命にすっぽりと浸かっているかもしれませんが、破壊/転覆の神話は生き延びているのです。
もちろん、サヴァイヴァル・リサーチ・ラボラトリーズ(SRL)のマーク・ポーリンのようなテクノ神話作家(ブリコラー)たちは、あなたが言わんとしている「破壊/転覆の神話」をもっとうまく具体化しているかもしれません。テクノロジーの残骸を盗み出し再び動くようにして作ったロボットで、軍産複合体に対してゲリラ戦を遂行するこの荒くれ者のテクノロジー主義者は、『モナリザ・オーヴァドライヴ』のスリック・ヘンリーのようなウィリアム・ギブスンの登場人物を通じて、アウトローのハッカーとともに、サイバーパンクの神殿に祀られてきました。
鉄屑野郎たちによって遂行されるテクノ革命というSRLが喚起するファンタジーの問題点は、そこに「赤い旅団」がかつてしたように「国家の心臓部に命中するように」首尾よく爆弾がしかけられているという、不釣り合いなまでに去勢された男のような信念が書き込まれていることです。いまや明らかなのは、ギー・ドゥボールの『スペクタクルの社会』からクリティカル・アート・アンサンブルの『電子の暴動』まで、権力の非線形のダイナミクスというポストモダン的な分析の基本的な前提は、権力が空化されている(エーテリアライズ)ということですし、(ウィリアム・S・バロウズ的な警句を使えば)支配は、体罰よりも、むしろ合意を生産するメディアのフィクションとともに大衆の想像力を植民地化することによって遂行されているということです。ポーリンは十二分にこのことに気がついています。SRLの公演では、官僚的な権力に対する儀式化された抵抗でさえも、その観客の心の中だけにせよ、明確な効果があるという前提に立っています。『エスケープ・ヴェロシティ』の中で私はSRLについての批評を「私は記号の身ぶりによる政治的潜在力を信じている」というポーリンの言葉で終えています。この引用は、スチュアート・ホール、ディック・ヘブディッジとそのグループによって理論化された文化政治学の闘争のスローガンの代わりに容易になるかもしれません。
残念なことに、記号の抵抗は、結局「記号」の抵抗でしかありません。それは、ミクロポリティカルな抵抗という名のもとにそのより広い文化的な領域を譲り渡し(さらに言えば、これはヴァーチュアル・コミュニタリアニズムと共有しているアキレス腱でもあります)、そして、意図にかかわらず、消費資本主義によって簡単に流用されてしまいます。この消費資本主義は、それがどれほど政治的潜在力に満ちていようが、驚くべき速度で、内臓、皮膚、素材そして多くの「記号の身ぶり」を消費します。ギブスンのサイバーパンクの標語を変形させれば、「商店街もまた、それぞれの、それぞれにとっての使い道を見出すのだ」ということです[☆8]。
最後に、商品とははっきりと見分けがつけられる抵抗の空間もまた、より毒性の強い政治的な侵入者を敵として生み出す消費資本主義というワクチンの中では、奇妙な新しい遺伝子を育む培養皿として機能することがあるかもしれません。アンドリュー・ロス[☆9]が『ストレンジ・ウェザー』で書いているように、『Mondo 2000』に代表されるようなサイバーデリックなカウンターカルチャーは、『ニューロマンサー』の中で描かれるチバ・シティの非合法地域、仁清のように、「合法的な産業デベロッパーのための実験的な測深板」として機能しています。それは、われわれを一周まわって『ワイアード』まで連れ戻し、サイバールンペンがマイクロ農奴(サーフダム)へ移行する際の文化的気密室(エアロック)としての役割を果たすのです。
政治的な戦略としては、こうした抵抗の儀式——あなたの用語に従えば「破壊/転覆の神話」は、国民国家の粗野な権力と、こういったものを急速に時代遅れなものに変えつつある多国籍巨大複合企業体との関係のうえに成り立っていますが、これは、たとえば、かつて紙と竹でできた放火装置をジェット気流に乗せてアメリカまで飛ばし、アメリカの森を焼き払おうとした日本の戦略が、同時に日本へのアメリカの原子爆弾投下との関係から成立していた、ということと同じようなものです。
こうしたことは、「不気味な欲望は、資本主義のひとつの大きな物語のなかで回収されて終わってしまうだけである」とか、われわれは「このナイーヴなテクノトピアな嵐が終わるまでただ待つ」べきだ、ということを意味しているのでしょうか? そんなことは絶対にありません。私は、ミクロポリティクスの抵抗に対する最後で最良の希望として、ポストモダン的なプリミティヴィズムや超ジェンダー的なアクティヴィズムや『スター・トレック』的なポルノグラフィや「おぞましいもの(アブジェクト)」をロマンティックに空想することに対しては疑いを持っています。その一方で、フランクフルト学派のマルクス主義を受け継いで、サイバーカルチャーを救いのない支配による一望監視型の悪夢として捉える破滅型の傾向もまた疑わしく思っています。さらに、アーサー・クローカーがジャン・ボードリヤールから受け継いだ馬鹿げた「不幸=憂鬱症(ディスフォリア)」については非常に懐疑的です。このとてもディストピア的なヴィジョンは、われわれを取り巻く社会経済環境の問題を解決する方法を何も提示しないばかりか、SF的なジャーゴンにペシミズムをくくりつけ、こうした問題をアカデミックなテーマパークの中の軽薄なアポカリプスに放り込んでしまっています。これこそが、ヴァルター・ベンヤミンが人間の「自己疎外が、自分自身の破滅をその最初の美的な喜びとして感じることができるまで来てしまった」と警告するときに語っていたことなのです。
われわれが最後にしなければいけないことは、隠れ家にしゃがみ込んで、「ナイーヴなテクノ・ユートピア主義者」と(美味しそうなメニューの)夕食のためのガイア的グロクトピア(筆者補註:grok=60年代のヒッピー用語で、もともとロバート・ハインラインが直観的把握という意味で用いた)というニュー・エイジ的な夢をもつ二層化した社会的現実、つまり、ますますホッブス的になっている現実を待ちかまえることです。こうした場所から抜け出す最初の一歩は、われわれがギングリッチ的な、あるいはトフラー的な自由放任主義の未来主義に火炎放射器を向けるところから始まるでしょう。こうした未来主義のおかげで、このわれわれ全体の運命は、市場の優しい憐れみか、われわれの希望を千年後の開花とやらにくっつけてしまうニュー・エイジ的なサイバーの樹に委ねられてしまっているのです。われわれは、この騒々しく汚れたいま現在のテクノロジーの未来に関する文化的な議論を設定し直して、もっと進歩的で実践的な未来主義を建設しなければなりません。
GL—— ヴァーナー・ヴィンジやK・エリック・ドレクスラーやハンス・モラヴェックに触れながら、あなたはサイエンスがそれ自体のテクノ終末論、あなたが「緊急脱出座席の神学」と呼んでいるものを生み出していることを指摘しています。こうした「明るい未来」の予言者にとって、テクノロジーは宗教的な側面をもっているようにも見えます。「聖なるものはマシンの中に生きている」というのが、北カリフォルニアのサイバーデリック・カルチャーとそのテクノ超自然主義的なファンタジーについての章の結論でした。サイバーカルチャーは、その宗教的な熱意を批判していないように見えます。フォイエルバッハもマルクスもニーチェもみんな、宗教とその制度について批判しているのに、『反マッケンナ論』はまだありません。ニュー・エイジはあまりにも深くテクノカルチャーに埋め込まれていて、ほとんど誰もこの語られない合意事項に疑問を挟まないようです。
もちろん、ポストモダンの思想家にそうすることを期待することもできません。現在の信仰体系に対抗するようなラディカルでデジタルな無神論を想像してもらえませんか? あるいは、そうしたサイバースペースの冷たい近代主義の説明はあまりにも耐え難く、それゆえ形而上学的な要素をわれわれが受け入れる必要があるのでしょうか?
MD—— さあ、とても私がフォイエルバッハやマルクスやニーチェと同等とは思えませんが、マッケンナについては喜んで剣を交えたいと思います(というのも彼は、千年王国のサイバーハイプのもっと有名な髭の予言者たちよりも、はるかにオリジナルで、限りなく説得力のある存在として私に衝撃を与えたからです)。事実、ちょうどオーストラリアのサイバー雑誌(ジン)『21世紀』のための原稿で一戦交えたところです。そこで、私はマッケンナのサイバーデリックなヴィジョンを、アーサー・C・クラーク的なSF神秘主義、ニュー・エイジの千年王国論、そして60年代の(特にノーマン・O・ブラウン)のディオニュソス的な「表現の政治学」から紡ぎ出されたサイボーグのための寝物語として理論化しています。多くのだまされやすいファンは彼の理論を字義通り受けとっているように見えるのですが、もしそうすれば、彼にはとても問題があります。というのも、彼の考えは、私がテクノ終末論——つまり緊急脱出座席の神学と定義したカテゴリーに明らかに陥っているからです。神学として理解すれば、彼の思索はほとんど因習的な輪郭をなぞっているだけです。たとえば、彼の話では、『原罪の物語』で描かれているように、幻覚作用のあるキノコという触媒のスパークを通じて太古の人類の言語が出現します。あるいは、マッケンナは、サウロがダマスカスに向かう途中で改宗するように「光でできたフラクタルでジオメトリカルな空間」を、そして、黙示録で終末論者が予言をするように「時間の終わりにおける超越的な物質」という彼の神学的なストレンジ・アトラクターを視覚的に経験をしています。
「デジタルな無神論」が、サイバーカルチャーに浸透している新グノーシス主義的な、あるいはニュー・エイジ的なテクノ超越論に対抗する必要があるのかどうかはわかりません。論理のかみそりは、それに関わっている具体的な政治という砥石によって研がれ、まさに正しく用いられるべきなのです。率直にいって、私が驚かされるのは、オンラインに加入している人数が人間の脳のニューロンの数と同じになったとき、ガイア的な精神が「生まれる」(それが実際何を意味しているのかはさておき)だろうというジョン・ペリー・バーロウの信念や、すべての人間がフィードバックと反復を通じて現実を最大限再デザインする能力があるという『サイベリア』でのダグラス・ラシュコフの主張を含むような事柄を誰もが無防備に信じ込もうとすることです。格好のいい新しいデータスーツにだまされてはいけません。これは、「サイキックな粘液の脈を打つウェブが存在し、われわれはすべてその一部分なのだ」という概念でP・J・オルークによって印象的に描き出された60年代のオー=ワオイズム(Oh-Wowism)とまったく同じなのです。
GL—— あなたのサイバーパンクの系譜学では、この(主に文学上の)現象はポップ・ミュージック、中でもパンクにその起源を持つとされています。しかし、歴史的に言えば70年代のパンクとテクノロジーの間には何の関係もないようです。また、パンクはサイバーパンクのようなナルシス的な個人主義を欠いていたように感じられます。
MD——『エスケープ・ヴェロシティ』の中でパンクとサイバーパンクが共有している文化的DNAについては、もっとうまく納得してもらえるようにきちんと証明していますが、ここで割り当てられた限られたスペースではそれほど多くのことができるわけではありませんので、こうした系譜学を辿ることに興味のある人には、私の本を読んでもらいたいと思います。とはいえ、パンクとサイバーパンクが共有していたものを簡単に言えば、都会の退廃した不愉快で貧乏な生活をロマンティックなものとして見せたことであり、実際の倦怠感と未来の衝撃を同じように平らにする効果を生んだことであり、何よりも重要なのは盗用の政治学と再活用されたガラクタ——消費文化のキッチュなゴミや科学と産業の壊れた残骸——破壊/転覆的な(サブヴァーシヴ)道具として利用することに対して抱いていた暗黙の信念でした。「メタル・マシン・ミュージック」と題された章では、伝説的なニューヨークの雑誌『パンク』に初期の頃のライターがこう書いていたのを引用しています。パンク・ロックは「現代の社会に“イエス”を言おうとしていた。ウォーホルのようにパンクは教養のある人が嫌ったすべてのものを受け入れた。それは、プラスティックであり、ジャンク・フードであり、B級映画であり、広告であり、金儲けだった」。こうしたパンク美学における一定の抑制——ロボット同化傾向(ロボパセティック)のある無表情(アンディ・ウォーホルが表明したロボットになりたいという欲望の『Mondo』のイコンによる回想)、タッパーウェアの消費主義と宇宙時代の楽天主義をともなった「ステップフォード」的な[☆10]郊外のニヤけた抱擁——は、サイバーパンクのディストピア主義と共鳴しながら、決して来ることのない約束の「明るい未来」をからかっていたのです。そこにある無表情で辛辣なユーモアは、『ガーンズバック連続体』でウィリアム・ギブスンがパルプSFの官僚的なファンタジーを、愛情をもって生け贄として捧げているのを思い出させます。こうした感受性は、またインディペンデント・グループ(彼らのICAでの1956年の展覧会「これが明日だ(This is Tomorrow)」は、完全なサイバーパンクの原型です)、リチャード・ハミルトンのようなポップ・アーティスト、J・G・バラードのようなニュー・ウェイヴの空想家による、ゆがんだ近代主義やジャンク・カルチャーの偏愛と重なりあっていたし、ザ・ノーマルやフライング・リザーズといったバンドにおいては神聖なものにさえなっていたのです。未来主義はもはや未来主義の形式を取らなくなっていたのです。
GL—— あなたのサヴァイヴァル・リサーチ・ラボラトリーズ(SRL)の批評を読んで気がついたのですが、あなたは、彼らをはるかに大きな運動である「インダストリアル」ムーヴメント(これもまた音楽にその起源をもちます)の枠組みに入れていません。インダストリアルの美学は、デジタル・テクノロジーと複雑な関係をもっており、80年代の典型です。非物質的なものの到来を予想しながら、それは廃棄された工場の暗闇、スクウォッティングや暴動の極端な状況、不要となった金属物の物質的な側面を賞賛しました。これはまた、ヤッピー(80年代の支配階級)の耐え難い明るさに対するディオニュソス的な回答と見ることができるかもしれませんが、あなたは、SRLの「機械主義(マシニズモ)」を告発し、彼らの「抑圧された男性のセクシュアリティ」について語っています。おそらく、彼らの観客は、ポリティカル・コレクトネス(PC)と完全な透明性の時代におけるSRLの低級なスペクタクルの暗さと汚さに魅せられているのでしょうが。
MD—— 私が、インダストリアル美学という美術史の文脈にSRLを位置付けていないという指摘については罪を認めましょう。言い訳としては、私の読者の大部分は SRLをその美学の出発点として位置づけている『RE/SEARCH』誌の必読号『インダストリアル・カルチャー・ハンドブック』を読んでいると考えていたということはありますが。サイバーカルチャーの神話的詩作——SRLの機械の破壊行為、D・A・テリエンの「コンフォート/コントロール」のサイバーボディ・パフォーマンス、インダストリアル・ダンス・ミュージック、『鉄男』から『ターミネーター』までのSF映画——が機械のイコノグラフィーを、情報社会への皮肉な隠喩として使っていることは否定できません。情報社会においては、そのテクノロジー的なトーテムであるコンピュータは表象というものに抵抗しています。コンピュータのつるつるとした特徴のない容器はとても謎めいているし、内部で行なわれている作業はあまりにも複雑でまた変化するので、それに対して想像力を組み立てることができません。こうしたポスト産業社会のエンジンを把握することができるのは、それが機械時代のへヴィ・メタルの中でイメージされるときだけなのです。
私の考えでは、『ターミネーター2』における液体金属T-1000(移動するシグニファイアがあるとすれば、まさにこれです!)だけがこの論理が間違っていることを示し、それゆえ、われわれの今を写すより正確な鏡となっています。それは、特徴のない銀色のマネキンへと液化して、それから、それが触るものになら何であれその完璧な複製となって固まります。これは、コンピュータによって約束されている当惑するほど液状の未来を象徴的に示しています。T- 1000は、労働や商品や果ては生命組織の遺伝子コードさえも、デジタル化を経て非物質化されるということによって特徴づけられるサイバーカルチャーの不気味な肉化を見せているのです。 SRLのスペクタクルが地底人的な「ディオニュソス的な」衝撃を爆発させることで「ヤッピーの耐え難い明るさ」に対抗しているというあなたの議論、つまりは、へヴィ・メタル・マッチョを告発するよりもその解放の側面によりはっきりと光をあてようという理解について、私はこう考えます。まず第一に、あなたが引用した問題箇所は私自身ではなく、SRLに対するフェミニストの批評家の非難です。私は、単にSRLのもっているアヴァンギャルド的な示威競争におけるジェンダー・ポリティクスを批判的に分析する文脈でそれを引用したにすぎません。
『エスケープ・ヴェロシティ』で現われる実際の文章はこうです。「しかし、ある人にとっては、マッチョ主義(マッチズモ)と機械主義(マシニズモ)の両面から同等に成立しているポーリンの美学は、自分の作品が拒絶していると彼が主張しているまさにテクノロジーの崇拝そのものを肯定してしまっている。あるフェミニストは、SRLの過剰な暴力騒ぎを“破壊様式を通じて演じられる抑圧された男性のセクシュアリティ”として非難している」。本書の中で議論しているように、私は、SRLがイデオロギーのストレート・ジャケット(犯罪者や精神病者が暴れないように腕を固定する上着)からくねくねと逃げ出す多原子価の現象だと思っています。たとえ、彼らが過剰な暴力騒ぎを楽しむために青臭いおそらく「男性の」欲望を演じているとしても(こうした本質主義的な告発には率直に言って私は困惑してしまいます)、このグループのパフォーマンスはテクノ革命のサイバーパンクのファンタジーと軍拡競争とアポカリプス的な「相互保証破壊」主義に関するブラック・コメディを演じていると思うのです。 マシン・アートについてのBBCのドキュメンタリー『パンデモニウム』で、私はSRLをピーター・パンの迷える少年たちとバーダー = マインホフ・ギャング[☆11]との交差点と呼びました。
正直に言えば、私は、理不尽な機械の殺戮の中のSRLの混じりけのない喜びに対して興奮します。それは美術界のメインストリームにある流行遅れの俗物的な道徳性を矯正し、元気づけるものです。政治的に正しく(ポリティカリー・コレクト)ブルジョア的な精神は、われわれの罪深い文化的快楽は、「救済する質」によって価値を判断されるべきだ、と主張します。その主題とそれゆえそれ自身の救いのなさに喜びを見いだすような「おぞましい」芸術は容認することができないのです。私はSRLを「ディオニュソス主義者」とは呼びたくありません。というのもこの言葉は、私の頭の中では不幸な『Mondo 2000』、ジム・モリスン・ファン・クラブの反響とともに鳴り響くからです。「青臭さ(アドレッセント)」のほうがもっと適しているように感じられます。そして、R・クラムやロバート・ウィリアムス、あるいはジョン・ベルーシが示したように、「青臭さ」とはその逸脱が最も激しくなるところで、まさにクリステヴァの定義するおぞましいものを具体化するのです。
GL—— あなたは、ステラークの「廃墟の身体」という概念を非常に真剣に捉えています。あなたは、神経精神科医が「私はステラークのファンタジーを病理学的なものだと思います。それは、世界破壊というファンタジー——完全に孤立化したいという極端でナルシス的なファンタジーの一般的なジャンルに属しています」と言うのを引用しています。どうして、彼の哲学を精神分析しているのですか? 明らかに、テクノロジーと権力の内化が彼の作品の主題です。それを理解するのに精神分析医は必要ではありません。もし、あなたが示唆しているように、ステラークがフーコーのいう権力の理想的な主体、分析可能で操作可能な「従順な身体(ドーサイル・ボディ)」を実体化しているのだとすると、彼はわれわれに自分たちのリアリティの一面を見せているだけにすぎなくなります。あなたが実際に疑問に付しているのは、われわれの社会のアーティストの役割です。ステラークのようなテクノロジー・アートはシニカルな反社会的な傾向を強めないでしょうか? もしそうなら、まさにそのためにそれは批判されるべきではありませんか?
MD—— 実際、私が神経精神科医でジョージ・ワシントン大学の神経学の教授であるリチャード・レスタック博士を引用した意図は、ステラークのポストヒューマンな狂詩曲(ラプソディ)の病理学的な本質を暴き出すことよりも、彼が提唱しているサイボーグ・アップグレードの基本的な現実的な可能性について検討することのほうに関係しています。(私の知る限りでは)これをした批評家はいないようです。レスタックは心理学的あるいは哲学的な見地からステラークのポスト進化論のシナリオを議論していますが、彼がそれに反駁するのは技術的で医学的な見地からなのです。
「テクノロジーと権力の内化」がステラークの永遠のテーマであることが自明だということ、そして私が、この時代のさらに電子的にコクーン化され、また人工補充物によって増強された存在によって育まれたポストモダン的な病理学である「シニカルな反社会的な傾向」にとって何かしら彼を身代わりにしようとしてきた、というあなたの指摘には、これ以上否定することはできないかもしれません。私が本の中で主張したことは、そういった点がステラークには失われているように見えるということです。彼は、彼の作品の神話解読的で記号論的な発掘に頑強に抵抗し、彼のサイバーボディのイヴェントを「ポスト進化論の」人間=機械の相乗(シナジー)の研究開発(R&D)として文字どおり受け取るように主張しています。彼は、技術用語によって彼のポストヒューマニズムの宣言をし、彼の作品の社会的あるいは政治的な解読を締めだすために「文脈抜きの」科学的な客観性に訴えようとしているのです。しかし、まさにそのイデオロギーにかき乱されない観念化や身体と機械の対立が「権力の政治」の外側で起こる、という概念そのものがサイエンス・フィクションです。真実は発見されるのと同様に構築されるものなのだという考え——すなわち、よりはっきりと言えば、中立的な価値をもった言説は文化的な前提によって色づけされている——というのは、サイエンスの最近の批評の根本的な考えなのです。
私は、「われわれの社会のアーティストの役割を疑問に付している」のでしょうか? もちろん、私が、彼のアートの中にレーダーの覆いのちょうど下を飛んでいくようなサイバーカルチャーの密かな政治学(ステルス・ポリティクス)をステラークに対して考えるように求めているという点では、そう言えるでしょう。ここで必要とされているのは、私も以前言ったように、ポストヒューマニズムの政治学です。ステラークのアートと思考は、彼がそう思っているように、サイエンスのために伝統的に維持されてきた価値基準から自由な文化的な真空の中に存在しているわけではありません。「社会的なものに対する場所(サイト)」ではないような身体の彼のSF的なヴィジョンは、フェミニズムの身体批判、人間のバイオテクノロジーの倫理に関する継続中の議論、そしてテクノロジーの進歩と絶え間ない拡張という資本主義の退屈な談義に対するエコロジーからの批判によって隅に追いやられているのです。
GL—— 『エスケープ・ヴェロシティ』の最後の最も長い章は、「身体政治学(ボディ・ポリティクス)のサイボーグ化」というタイトルです。そこであなたは、「サイバーカルチャーにおいて身体は浸透性のある皮膜であり、その清潔さは冒涜され、神聖さは犯されている」と書いています。またあなたは、身体は「妊娠中絶の権利、胎児細胞の使用、エイズ治療やその他をめぐるイデオロギーの論争のための闘争の領域」となった、と記しています。あなたの考えでは、サイボーグの熱狂的支持者は重要な問題を見逃しているようです。オルランやクローカー夫妻は、スコット・ブカットマンが指摘したように、「危機に瀕した現実の身体」があるということを忘れているのです。もはや、奇妙な新しい身体とテクノの連結を夢見ることは不可能なのでしょうか?
MD—— このことは、『サロン』のインタヴューでハワード・ラインゴールドが、私に「ポストヒューマニズムのおかしな側面」について訊ねた質問に関わっています。ポストヒューマニズムが(少なくともいまのところ)すべてサイエンス・フィクションの概念であるということにわれわれは決して十分に思いいたることができないのですが、こうしたポストヒューマニズムの誘惑とは、身体をもたない無定位運動(キネシス)と情報による眩暈という未来像、つまりは強力な並列処理の知力とサイボーグ的な筋力というマーヴェル・コミックのヴィジョンなのです。チャールズ・プラットが彼の忘れられない小説『シリコン・マン』の中で描き出した情報形態のひとつのように再変身し、サイバースペースのフラクタルな地形を非肉体化して曲芸飛行したいと夢見なかった人がいるでしょうか? あるいは、サイバネティクス的に無茶苦茶に精神を強力にして、全ての人間の知識をその羅針盤の中に流し込み、チェンとエン[☆12]の秘密の性生活からJFKの頭蓋骨の傷口の穴、果てはアインシュタインの脳の神経細胞まで飛び跳ねることができたら、といった考えに魅せられなかった作家がいるのでしょうか? 私は、特にO・B・ハーディソンの崇高な、あまりにも寂しいヴィジョンに心を奪われています。それは、その『天窓を抜けて消えていく(Dissapearing Through the Skylight)』の最後で描かれる、人間の意識が遠い無人観測宇宙船にダウンロードされて、ソーラー船に乗って無限の縁を飛行していくというヴィジョンです。しかしこの崇高さの代償は何なのでしょうか?
プラットが描いた、自分自身の意志に反してダウンロードされ、自分が二度と自分の妻や子供を自分自身の手で抱きしめることができないコンピュータ・メモリーの電子の雲だと気がつく男の痛々しく悲しい記憶は、これまで私にずっと取り憑いていました(左翼知識人はその雲を逆境のなかの希望の光として見ることができる……んですよね?)。
GL—— 多分、サイバーカルチャーにおける流言と誘惑的な像の第一段階が終わろうとしつつあります。しかし、いまなお、われわれは誘惑に潜む法則を理解し、欲望の経済を否定しないようにする必要があります。多分、問題はサイバーカルチャーのはっきりとしない社会的経済的位置にあります。それはマスカルチャーの一部でもなければ明確に支配階級に政治的に敵対しているわけでもありません。このことは、ファンタジーの過熱しすぎた経済、指示対象のない記号の生産のための空間を残しています。あなた自身、エクストピア主義者のようなカリフォルニアのテクノ超自然主義の白日夢をまじめに受け取るべきかどうか決めかねているようです。その一方で、あまりにも多くのサイバーな予測の土台を作っている「第三の波」の経済という『ワイアード』的なヴィジョンをどの程度まじめに受け取っていますか?
MD—— 私は、知的恍惚にあるニュー・エイジの予言やこのインタヴューで語ってきたじわじわと増えつつあるサイバー資本主義者を、権力のジョイスティックを握っている人たちが受け取っているのと同じくらいに、真剣に受け取っています。私は、こうした考えが重要であると信じ、企業の権力者がギングリッチ=トフラー的なレトリックをまじめに受け取り、それにしたがって経営戦略を立てているという程度には、『ワイアード』に媚びられ略歴が紹介されている自由放任主義の未来主義者たちを、真剣に受け取るべきだと実際に信じている、救いようのない知識人まがいのひとりです。より多くの政策が企業のロビイストによって作られるにしたがって(最近では、その内の何人かは文字どおり、彼らの不正資金——いやいや、キャンペーン献金が買収した法律を書くことを要求されてきました)、誰が企業の権力者の耳元で囁いているのかという問いが、われわれにとってもどうでもいいことではなくなっています。あの不便な「第二の波」の迷惑の元凶だった国家という規制の象徴から解き放たれた多国籍企業の画一的な慈悲に自分たちの未来をまかせたくはないのです。
私は『ワイアード』をルパート・マードックのメカゴジラ版だと思っているのでしょうか? そうではありません。しかし、経営者の導師(グル)トム・ピーターズは最近では『ワイアード』の編集者でミーム的な哲学者であるケヴィン・ケリーと同じ調子の曲を歌っています。ジョージ・ギルダーもそうです(キーこそ違いますが)。そして彼らのあごの外れるような公演料からも企業文化がピーターズやギルダーを非常に本気で受け取っていることがわかります。明らかに、国家をほとんどなくなるぐらいまでにダウンサイジングするという『ワイアード』的な自由放任主義的ヴィジョンが役員会議室や都市生活者の内部の耳を捕らえています。このことが、——今日の遺伝子の比喩を使えば、身体政治学(ボディ・ポリティクス)におけるレトロウィルスと同様に——私の中にこうした考えを真剣に受けとめる価値があると思わせるのです。
■原註
★1——Mark Dery. Culture Jamming: Hacking, Slashing and Sniping in the Empire of Signs. Open Magazine Pamphlet Series, 1993.
★2——Mark Dery (ed.) Flame Wars: The Discourse of Cyberculture, Duke University Press, 1995.
★3——Mark Dery. Escape Velocity: Cyberculture at the End of the Century, US: Grove, UK: Hodder & Stoughton, 1996.[邦訳=角川書店より]
■訳註
☆1——人間と機械の過激な融合をポストヒューマニズムとして唱える,ロサンゼルスの雑誌『エクストロピー』を中心とした人々.
☆2——Degirati=Degital+Literati(知識階級)からなる造語.
☆3——ハキム・ベイの用語.この用語によって,彼は恒常的・永続的に自律した自由空間の代わりに,一時で消滅することを前提とした自律的空間を組み立てることを提唱している.
☆4——『ワイアード』の編集者ケヴィン・ケリーの本のタイトル.
☆5——アメリカのカーニバルや村祭で人気のアート.紙を回転盤に固定し回転させながら上からいろいろな絵具を垂らして作る,サイケデリックな渦巻状の抽象画.
☆6——Day Glo=Day Glow.蛍光色を用いた60年代的グラフィックス.
☆7——アメリカで人気の子供テレビ番組『マイティ・モーフィン・パワレンジャー』(『ゴレンジャー』の外国向けリメイク)の中で主人公が変身するときに使われるCGのタイポグラフィー.
☆8——原文は“the strip mall finds its own uses for things, too”で,ちなみにもとになったギブスンの一文は,“the street finds its own use for things”.
☆9——テクノロジー,文化,エコロジーと政治の問題を論じているカルチュラル・スタディーズの論者.プリンストン大学で英語とカルチュラル・スタディーズを教える.『ストレンジ・ウエザー』の他の著作に No Respect: Intellectual & Popular Culture (Routledge, 1989),共編に Techno Culture (University of Minnesota Press,1991).
☆10——郊外生活を描いたブラック・コメディ映画『ステップフォードの妻たち』で見られるような.
☆11——70年代ドイツの極左グループ.
☆12——19世紀のアメリカのサーカスにいた有名なシャム双生児.
(マーク デリー・批評家/ヘアート ロフィンク・メディア論/
訳=もうり よしたか・カルチュラル・スタディーズ)
[ホームページ・リンク]
http://markdery.com/
- Intellipunk
- By intellipunk / Dec 25, 2011 1:53 pm
- Home » Tags » マーク・デリー
- Search
- CJharpo Movie
-
2010.2.27 反新宿署!高円寺路上大パーティざまあみろデモ 【予告編】-
覚せい剤撲滅プロパガンダ 東映編 -
2006/9/16 家賃をタダにしろ!中野→高円寺一揆!予告編
家賃廃止要求デモ!
- Favorite
-